\ 開発会社選びで失敗したくない方へ /
システム開発・WEB制作を発注する際の“正しい選び方”を
全8回の無料メルマガでお届けしています。
- よくある失敗例と回避法
- 信頼できる会社を見極めるポイント
- 外注が初めての方も安心
\ 登録はこちら!名前とメールアドレスだけ /
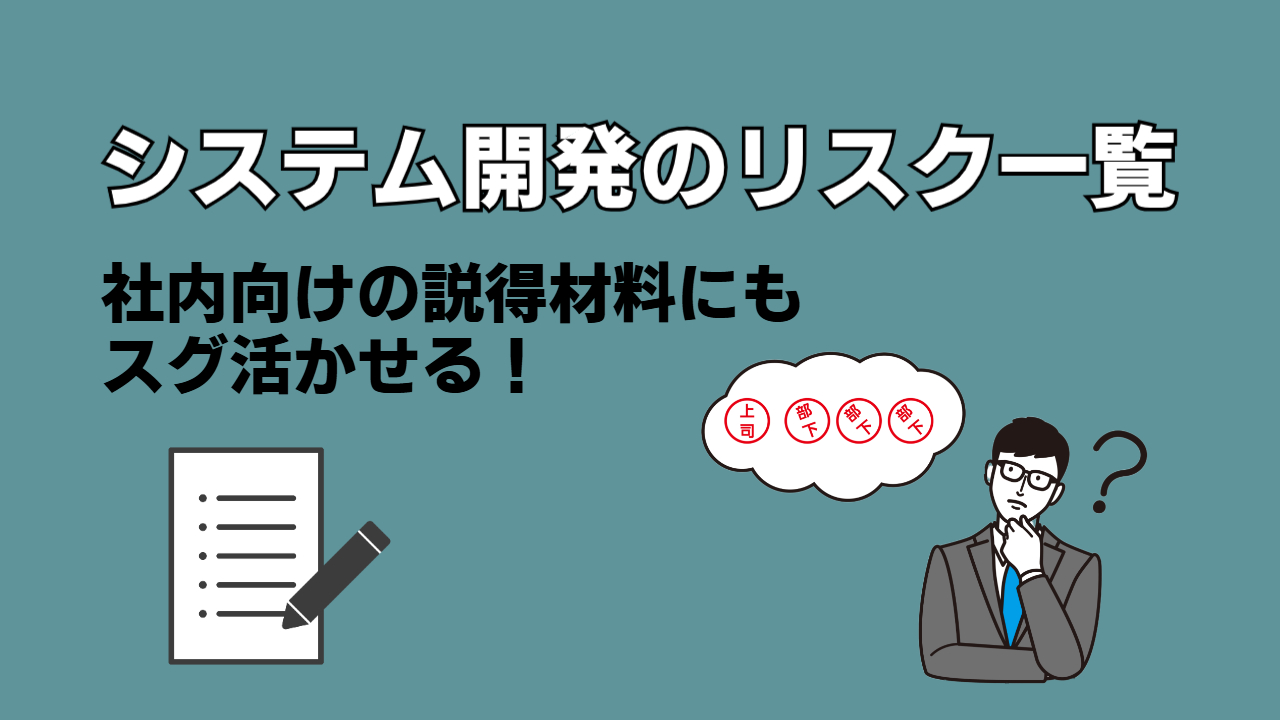
\ 開発会社選びで失敗したくない方へ /
システム開発・WEB制作を発注する際の“正しい選び方”を
全8回の無料メルマガでお届けしています。
\ 登録はこちら!名前とメールアドレスだけ /
システム開発は、企業の業務効率化や売上拡大に直結するため、DX化が推進されている昨今は需要が高まっています。しかし、失敗すれば多額のコストや社内混乱を招いてしまうようなリスクも伴います。

何に注意すればいいのか分からない



社内で企画を通すには、もっと説得力が必要だなあ
そんな方に向けて、よくある失敗例を交えながら、開発時に押さえておくべきリスクを一覧形式で整理しました。
稟議書や提案資料にもそのまま活用できるテンプレートもご用意しています。
リスクを見える化して、御社の状況に合った正しいDX導入の判断材料になれば幸いです。
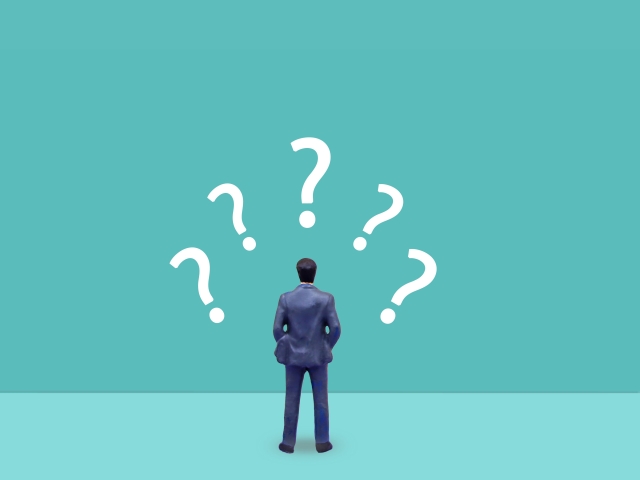
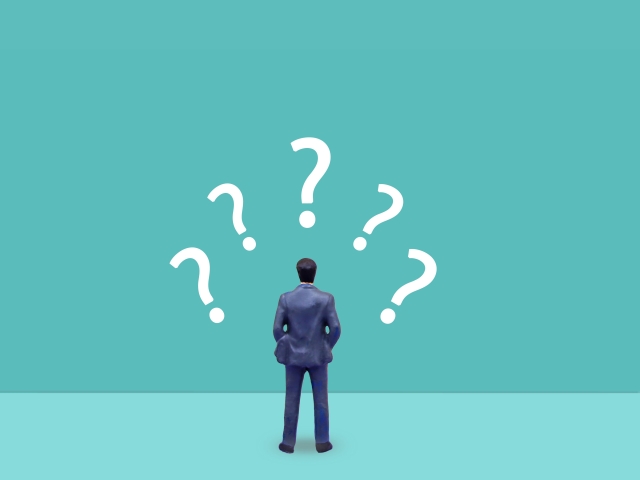
では、まずはシステム開発でよくある失敗について、具体例を挙げながら詳しく探っていきます。
では、どんな失敗例があるのかを3つの例にて紹介していきますね。
ある企業では、業務の効率化を目的に販売管理システムのリニューアルを進めました。
要件定義は経営企画部が担当し、開発もスケジュールどおりに完了したのですが、実際に使う現場スタッフからは「操作が面倒でわかりにくい」、「入力に手間がかかる」など不満の声が噴出。
結果としてシステムはほとんど使われず、旧Excelでの運用が続行することになりました。
現場を知らない部署によりシステム開発の指揮が執られてしまったため、現場が期待していた“使いやすさ”が設計段階で考慮されていなかったのです。
開発コストはかけたのに業務改善にはつながらず、要件定義段階での認識のズレから深刻な失敗が生じてしまいました。
BtoB向けECサイトの開発プロジェクトを進めていたある企業の当初の見積もり額は1,200万円でした。
開発を進めていく途中で「この機能も追加したい」、「ここの画面も変更したい」と仕様変更が相次ぎ、その都度予算をよく確認せず機能重視にしてしまったため、最終的に請求額は約2,000万円にまで膨らみました。
プロジェクト途中では「ここまで来たら止められない」という心理も働き、判断が曖昧になってしまったと言います。
契約形態が準委任だったこともあり、追加費用に歯止めがかからなかったのです。
最初に機能の優先順位を明確にしなかったことと、契約書に「仕様変更時のルール」を盛り込んでいなかったことが、予算超過の主な原因でした。
ある中堅企業が新しく勤怠管理システムを導入しました。
しかし、リリース初日から不具合が多発し「正しく打刻できない」、「勤務時間が集計されない」といった声が相次ぎました。
原因は納期を優先した結果、十分なテスト期間を確保できなかったことでした。
また、開発会社任せで社内のレビュー体制が整っておらず、成果物の改善点などを共有する過程がなかったことが問題を悪化させました。
この結果、再テストと修正対応で1か月以上の業務混乱が発生。
品質管理と検証プロセスの軽視が、現場の混乱と信頼低下を招いてしまいました。
また、無理なスケジュールによる開発はシステムの品質低下やテスト工程を省くことを誘発してしまうため、スケジュール管理にも注意が必要です。
では、上記の3つの例において「なぜ起きたのか」、「どうすれば防げたのか」という視点で解説していきます。
この失敗の本質は「ユーザー視点の欠如」と「要件定義段階での認識のすれ違い」にあります。
開発をリードしたのは経営企画部でしたが、実際にそのシステムを日常的に使うのは現場の担当者ですよね。
つまり、システムに求められる“使いやすさ”や“業務の流れに即した操作性”を正しく理解して要件定義に落とし込むことができていなかったのです。
また、「現場の声=使いやすさに直結する情報」は、紙の資料や定例会議だけでは把握しきれないにもかかわらず、深掘りせずに進めてしまいました。
このような失敗を防ぐためには、要件定義段階から現場のキーパーソンを巻き込み、ワークフローや課題点を可視化した上で“共通認識”を持つことが大切です。
さらに、開発途中でも操作性を確認できるステップを設けることで、より現場に即したシステムを確認しながら開発することが可能になります。
開発費用の予算超過が起きた背景には、仕様の追加・変更に対するルール整備不足と、初期の要件定義における詰めの甘さがあります。
開発途中で「こうするともっと良いのでは」と後から気付く要件は発生しますが、それらをすべて受け入れていては、開発コストがいくらあっても足りません。
本来、プロジェクト開始時には「必須機能」と「優先度の低い要望」を明確に分類し、どこまでが初期開発対象かを線引きしておく必要があります。
契約時に「追加開発が発生した場合の対応方法(見積・承認・費用)」を文書で明記しておくことも効果的でしょう。最初にしっかり取り決めておくことで、結果としてムダな支出を防ぐことに繋がります。
この失敗の背景には、開発工程における「テスト」の重要性が過小評価されていたことがあります。
開発スケジュールがあまりにギリギリになり、リリースすることが目的になってしまうと、テストは削られる工程になりやすいです。
しかし、不具合が本番稼働後に発覚すれば、ユーザーの不信感や業務への影響は計り知れません。
解決策としては、テストを「最終確認」ではなく、設計時から意識して組み込んでいくことでこのような問題を防げます。
たとえば、要件をもとにテストケースを先に設計する「テスト駆動」の考え方や、第三者によるレビュー体制を導入することで、品質担保の精度が高まります。
また、ユーザーテストを事前に実施することで、ユーザーによる想定外の操作や使い方も拾い上げることができ、未然にトラブルを防ぐことができます。システムの活用方法に合ったテスト方法を開発会社に相談するようにしましょう。


このように、例を挙げて失敗と解決策を解説してきましたが、そもそもリスクを洗い出すことによってどんなメリットを得られるのでしょうか?
リスクを洗い出すことは、以下の5つのメリットがあります。
開発プロジェクトで起こりうるリスクを事前に把握しておくことで、同じ失敗を繰り返さずに済みます。
特に、過去に多い失敗(要件のズレ、予算超過、テスト不足など)は、「備えるだけで避けられる」ものも多いため、洗い出しの効果は非常に高いです。
「なんとなく不安」ではなく、具体的なリスクとその対策をセットで提示することで、上層部や他部署との合意がスムーズになります。
稟議書や会議資料にも転用でき「このプロジェクトは準備がしっかりしている」と評価されやすくなります。
開発会社と契約を結ぶ際に、事前にリスクを理解していると「仕様変更が起きた場合はどうしますか?」など、依頼会社側から具体的な交渉ができるようになります。
結果として「知識がないから」と開発会社側から軽視されることも減り、「認識が違った」というトラブルを回避できます。
開発が進む中で「この仕様は本当に必要か?」、「納期を優先するべきか?」と迷う場面は必ずあります。
そういった場面でも、あらかじめ洗い出したリスクと対策が“判断の軸”になります。
場当たり的な判断を防ぎ、冷静な意思決定ができるようになります。
最終的には、リスクの“見える化”が、関係者全体の意識統一と行動の最適化につながります。
その結果、納期・品質・コストの3要素をバランスよく保った開発が可能になります。


では、リスクと回避策の一覧と、資料に使えるテンプレートをご用意しました。
よろしければ、ぜひご活用ください。
考えられるリスクを15項目ピックアップしてみました。
「リスクの内容」、「概要」、「回避策」を表にしているので、参考になれば幸いです。
| リスクの内容 | リスクの概要 | 回避策 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 要件の曖昧さ・認識のズレ | 部署によって「必要な機能」の捉え方が異なり、出来上がったものが「使えない」と評価される原因に。特にヒアリング不足で発生しやすい。 | システムを使う現場の人に話を聞いて、「必要なこと」を事前にしっかり整理してからスタートする |
| 2 | 仕様変更の頻発 | 開発途中で「これも追加したい」「やっぱりこう変更して」と要望が変わり、工数が膨らむ。優先度整理や意思決定が曖昧な場合に多い。 | 最初に「今すぐ必要なこと」と「あとで考えたいこと」を分けて、途中で追加が出たときの対応ルールを決めておく |
| 3 | 予算の超過(追加費用の発生) | 契約外の機能追加が続き、当初の見積を大きく上回る請求が発生。「あとから請求されるとは思わなかった」という声が出やすい。 | 追加の作業が出たときは、その都度いくらかかるか見積もりを出してもらい、会社としてOKを出してから進める |
| 4 | スケジュールの遅延 | 承認の遅れや仕様ブレ、テスト不足など複合要因により、リリースがずれ込み「業務が始められない」と社内混乱を招く。 | スケジュール表を作って、どこまで進んだかを定期的にチェックする会議を開く |
| 5 | UI/UXの不満・利用定着の失敗 | 操作が複雑だったり、導線が直感的でなく「現場が使いたがらない」状態に。結果として旧システムやExcelに逆戻り。 | システムが完成する前に、画面の見た目や動きを実際に触って確認できるようにしてもらう |
| 6 | 開発会社とのコミュニケーション不足 | 質問の意図が伝わらない、成果物が期待と違う、進捗が見えない…といった問題が発生しやすく、信頼関係が崩れがち。 | 週に1回など、定期的にオンライン会議を開いて、進捗や気になる点を共有する |
| 7 | テスト不足・リリース後の不具合発生 | 「正常動作しかしない前提」で本番に突入し、バグや不整合が発覚。特に例外系や複数パターンの検証が抜けやすい。 | 完成後すぐ使い始めるのではなく、社内で試してみて問題がないかチェックする時間を必ず取る |
| 8 | 属人化・ナレッジの属人依存 | 担当者しか分からない操作・設計になっており、退職や異動で「誰も中身がわからない」状態に。引き継ぎ不能になる。 | 特定の人しかわからない状態を避けるために、作業のやり方や設定内容を必ず文書にして残す |
| 9 | ドキュメント不備・納品物が整っていない | マニュアル・仕様書が未整備で、保守や改修時に「どう動いているか分からない」と毎回調査が必要になる。 | 「マニュアルや設計書などは納品してもらうもの」とあらかじめ契約書に書いておく |
| 10 | 契約内容の不備・不明確な責任分担 | 「誰が・どこまで・いつまで対応するか」が曖昧な契約で、トラブル時に責任の所在で揉める。 | 「何をどこまで作るか」「トラブル時は誰が対応するか」などを契約書で明確にしておく |
| 11 | システムが業務フローに合っていない | 実際の業務に沿っておらず、「戻るボタンがない」「入力順が現場と違う」など、現場にストレスが生じる。 | 実際の業務のやり方(順番・入力内容)をしっかり把握・共有し、システムの画面設計をしてもらう |
| 12 | 保守・運用体制が未整備 | リリース後にエラー報告があっても、誰が対応するか決まっていない。連絡フローが不明確で復旧に時間がかかる。 | システムの不具合があったときに「誰に・どう連絡するか」を事前に決めておく |
| 13 | セキュリティ対策の甘さ | アカウント管理がずさん、通信が暗号化されていない、SQLインジェクション対策が未実装など、基本的なセキュリティの抜けが多い。 | パスワードの管理や、アクセスできる人の制限など、基本的な安全対策を開発段階からお願いする |
| 14 | KPIや導入効果の不明確さ | システム導入後に「効果があったのかどうか」が見えず、結果として経営層の理解や追加投資につながらない。 | 「導入後に何が良くなっているか」を数字でわかるようにして、目標を最初に決めておく |
| 15 | 外部ツール・サービス連携の不具合 | 他社システム(API・CSV連携など)との仕様変更やバージョン不整合で、連携がうまく動かなくなる。 | 外部サービスと連携する部分については、事前に仕組みや仕様をよく確認してから導入する |
では、資料に使えるテンプレートをご用意いたしましたので、参考にしてみてくださいね。
実際に作成するときには、開発会社と直接相談しながら作るほうが、具体的に内容を詰めやすくなります。
WEBシステム導入における開発概要
現在、情報が複数ページや部署に分散しており、ユーザー視点での情報取得が困難な状態にある。
ポータルサイトによって、一元化された情報発信を実現し、問い合わせ・申込の増加を狙う。
マーケティング部・営業部から「Web上の導線に課題がある」との声が多く、社内でも顧客管理や問い合わせ対応の属人化が指摘されている。改善にはユーザー目線の情報設計が可能なCMS型ポータルが必要。
当社に関連するサービス情報を集約し、ユーザーとの接点を強化するためのポータルサイトを新規開発する。
現在コンバージョン率(CVR)が1%のため、翌年度には2%になるよう目指す。
スケジュール:要件定義〜公開まで約5ヶ月を想定
契約形態:請負契約+保守サポート1年間
開発範囲:設計、画面構築、CMS実装、スマートフォン対応
予算見積:XXX万円(税抜)
| リスク内容 | 回避策 |
| UI/UXがユーザーに合わない | 開発前にワイヤーフレーム・モックを用意し、関係部門でレビューを実施 |
| 要件のブレによる工数超過 | 要件定義段階で機能の優先度を整理し、変更時の見積・承認ルールを設定 |
| 納期遅延 | マイルストーン制の進捗管理と定例確認会を導入 |
基幹システム導入における開発概要
現行システムは10年以上前の設計で、改修性・拡張性が低く、現場での手作業が依然多く残っている。
運用コストや人的リスクが高まりつつあるため、システムの全面見直しが必要と判断。
現場から「操作に手間がかかる」「帳票出力が不安定」などの声が多く、経理・営業・物流それぞれの現場で非効率が発生。将来的な業務拡張に備えた柔軟な構成が必要。
受発注・在庫・請求業務を支える基幹システムを刷新し、業務の属人化解消と効率化を図る。
現在人件費が売上総利益の30%を占めているため、翌年度には15%になるよう目指す。
スケジュール:7ヶ月(要件〜移行完了まで)
導入後:保守・運用体制もあわせて構築予定
開発範囲:業務ヒアリング、要件定義、DB設計、画面設計、検収支援
開発費用:XXX万円(税抜)
| リスク内容 | 回避策 |
| 現場の業務にフィットしない設計 | 部門横断ヒアリング+業務フロー図の作成で、要件とのずれを防止 |
| 属人化による引き継ぎ困難 | 仕様書・マニュアルの整備を義務付け、複数人での運用想定設計 |
| 運用開始後の問い合わせ混乱 | サポート体制(窓口・対応フロー)を明文化し、事前周知 |
アプリ導入における開発概要
問い合わせ対応・予約管理・現場対応などにおいて、紙や電話に依存しているため、顧客対応スピード・社内業務の生産性に課題がある。アプリ活用により、利用者との接点をデジタル化する狙い。
競合他社においてもアプリ提供が進んでおり、利便性・ブランド体験の差別化が急務。
また、社内からも現場対応業務の簡素化ニーズが高まっている。
顧客体験の向上/現場業務の効率化を目的に、スマートフォンアプリを開発・提供する。
現在コンバージョン率(CVR)が1%のため、翌年度には2%になるよう目指す。
対象OS:iOS/Android 両対応
スケジュール:要件定義〜公開まで約5ヶ月を想定
契約形態:請負契約+保守サポート1年間
初期開発費用:XXX万円
保守費用:月額XX万円(バグ対応・アップデート対応)
| リスク内容 | 回避策 |
| リリース後の不具合・バグ対応 | 開発後に十分な社内検証(実機テスト)を行い、段階的なリリースを実施 |
| アプリが使われない | UI/UX設計段階で現場・ユーザーの声を反映、導線を簡潔に設計 |
| OSバージョンアップに伴う不具合 | 保守契約にOS対応アップデートを含め、長期的な運用を見据える |
よくある失敗例を交えながら、開発時に押さえておくべきリスクを一覧形式で整理し、資料にもそのまま活用できるテンプレートをご用意しました。
システム開発を行う上で、しっかりとリスクを社内で共有したうえで対策を練ることは必須です。
開発会社にすべてを丸投げしてしまうのではなく、社内でもしっかりと取り組む姿勢があることで、よりよいシステム作りが可能となります。ぜひ参考にしていただければ幸いです。
また、弊社では開発も承っていますが、さまざまなシステム開発会社のご紹介も行っております。
複数見積もりも可能ですし、開発会社の紹介を受けるのに手数料などは一切かかりません。
もしよろしければ、ぜひご相談くださいね。



気になっているけど、まだ動けていない…
そんな方に向けて、全8回の無料メルマガを配信しています。
外注初心者でも安心して使える開発会社選びの考え方と
失敗しないためのチェックポイントをまとめました。
\ 名前とメールアドレスだけ!登録はこちら /