\ 開発会社選びで失敗したくない方へ /
システム開発・WEB制作を発注する際の“正しい選び方”を
全8回の無料メルマガでお届けしています。
- よくある失敗例と回避法
- 信頼できる会社を見極めるポイント
- 外注が初めての方も安心
\ 登録はこちら!名前とメールアドレスだけ /
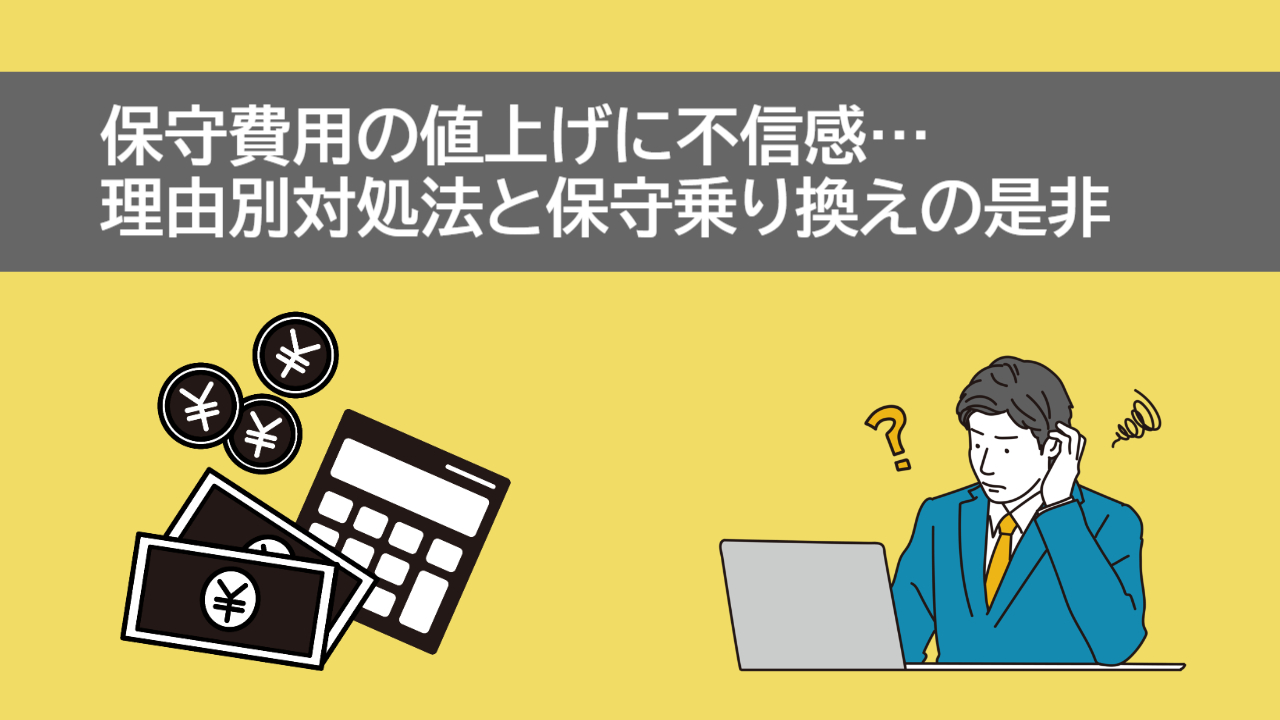
\ 開発会社選びで失敗したくない方へ /
システム開発・WEB制作を発注する際の“正しい選び方”を
全8回の無料メルマガでお届けしています。
\ 登録はこちら!名前とメールアドレスだけ /

来月から保守費用が上がります。
――開発会社からの突然の通知に、戸惑いやモヤモヤを感じた方が、この記事を見てくださっているのではないでしょうか。
これといったトラブルもなく、これまで通りの運用をしていただけなのに「なぜ今、値上げなのか?」
説明も曖昧で「本当にこの金額が妥当なのか」と疑問に思ってしまう………。
とはいえ、保守は業務を支える大事な土台だし、簡単に切り替えるわけにもいかず、悩みは深まるばかり。
SELECTOの運営会社である株式会社セルバも多くのクライアントと保守契約を結んでいるので、そんな想いを抱える方のために、この記事では「よくある値上げの理由」と「その背景にどう向き合えばいいのか」を整理しつつ、「このまま続けるべきか」「乗り換えるべきか」の判断軸をわかりやすくお伝えします。
感情だけに流されず、納得感ある判断をするための一助になれば幸いです。
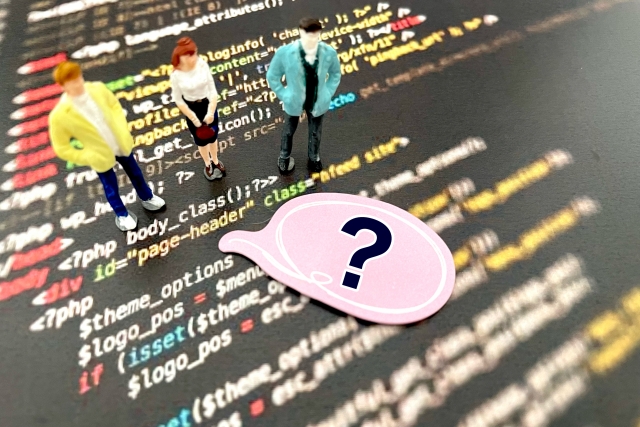
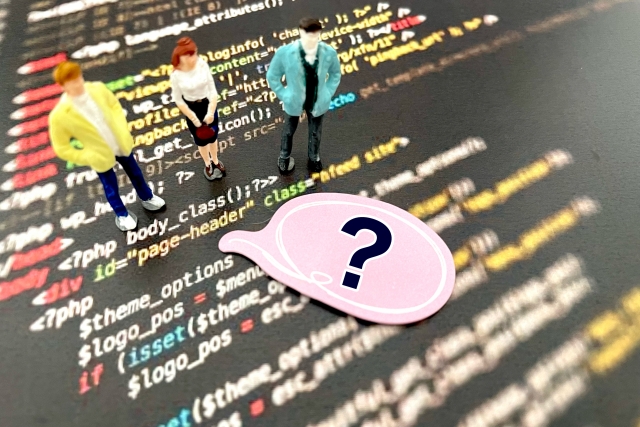
ではまず、値上げの理由とその背景について解説していきますね。
よくある値上げの理由
保守費用の値上げ理由としてよく挙げられるのが「人件費や物価の上昇」です。
一見すると



それは開発会社の経営努力で吸収すべきでは?
と感じてしまうかもしれません。
しかし、IT業界では近年、エンジニア不足が深刻化しており、優秀な人材を確保し続けるためには、報酬水準の見直しが避けられない状況になっています。
IT人材の不足は、現状約17万人から2020年には約37万人、2030年には約79万人に拡大すると予測され、今後ますます深刻化すると考えられている。
引用元:経済産業省・IT分野について
特に保守業務は、障害発生時の対応やセキュリティ監視など、表には見えにくいのですが責任の重い業務です。
その業務を安定的に動かし続けるためには、組織の強化や育成が必要となり、どうしても一定のコストがかかってしまいます。
また細かな話かもしれませんが、クラウドサービスや通信機器の価格改定、物価高騰による各種経費の増加も、保守コストに大きく影響してしまっています。
もちろん、開発会社としても値上げは簡単な決断ではなく「長く良い関係を築くために必要な見直し」として、やむを得ず提示しているケースがほとんどです。
こうした背景を踏まえると、単なる“コスト増”ではなく、“体制維持と品質担保のための必要経費”として考える必要もあるでしょう。
保守費用の見直し理由として「システム規模の拡大」が挙げられることがあります。
これは単に画面や機能が増えたというだけでなく「保守の手間や範囲が広がっている」ことを意味します。
保守サービスを受ける側からすると



特に大きな機能追加や仕様変更はしていないのになあ…
と感じることもあるかもしれませんが、実は小さな要望や環境の変化でも、保守環境が大きく変わることがあるのです。
例えば
など、細かな要望ではありますが、これらには
といった保守の手間や範囲の拡大が起こります。
しかし、これらの要望は、システムを活用しているからこそ起こる要望ですよね。
見方を変えると、それだけ事業や会社が成長しているのだと捉えられると思います。
保守費用の見直しが発生するタイミングとして意外と多いのが「契約更新時」や「初回割引の終了」です。
開発会社の中には、導入初期のハードルを下げるために初年度はあえて低めの保守費用を設定し、システムが軌道に乗るまで支援する方針を取っているケースがあります。
この段階では「お試し価格」のような位置づけであり、“2年目以降は本来の水準に戻す”というのはある意味で想定された流れともいえます。
システム導入から1年経てば、実際の運用実績や対応履歴をふまえて、作業範囲や対応体制を再検討する機会も必要になってきます。
もし初年度が特別条件だった場合には、その旨が契約書や見積書に記載されていることが多いので、あらためて確認してみるとよいでしょう。
このようなケースの場合、それは「約束された期間が終わった」という事実に基づくものであり、決して一方的な値上げとは限りません。
その内容が契約に明記されていたか、説明が丁寧に行われたか、そしてその費用に見合う価値が今も提供されているのかを見極めることが大切です。
システムは一度作って終わりではなく、時代の変化に合わせて変わり続けるものです。
そんな中、保守費用の見直し理由として挙げられるのが「新技術への対応」や「インフラ環境の変更」です。



でも、新技術やインフラ変更って、開発会社やクラウド提供側の都合じゃないの?
と思う方も多いですよね。
では、これらに対応しなかった場合はどのようなリスクがあるかをお伝えしておきます。
新技術やインフラ変更に対応しなかった場合のリスク
これらが起きてしまってからでは、保守や改修作業により多くの時間と労力がかかってしまうため、アップデートしないことにより余計なコストをかけてしまう恐れがあります。
アップデートの対応は、何もしていないように見えて実は裏で技術的な対応をしています。
もし費用の見直しがこのような理由によるものであれば、開発会社の対応内容を丁寧に確認したうえで、必要なアップデートとコストのバランスを見極めることが重要となります。
保守費用の見直し理由として「サポート内容の見直し」が挙げられることもあります。
これは単に費用を上げるというよりも、提供するサービスの範囲や質を再定義するタイミングで発生する場合が多いです。
システムを運用し続けていると、どうしても開発時には不要だと思っていた技術が必要になったり、何かエラーが起こった時に対応体制を見直したり、保守レポートでは分かりにくい部分の説明を求めるために定例ミーティングを増やしたりする必要が出てくるかもしれません。
こうした“裏方の強化”は直接的な成果として見えにくい一方で、いざというときに事業を止めないための大きな支えとなります。
また、セキュリティ脅威の増加や外部環境の変化に伴い“開発会社にこれまで以上の対応が求められる時代になっている”という背景も存在します。
それらにその都度対応するとなると、自ずと保守サービスの拡大が必要になることが理解できると思います。
そのため、保守サービスの「量」と「質」に見合った価格設定への見直しは避けられないのが実情です。
値上げに対して不安を感じる場合は「具体的にどんな内容が追加・強化されたのか?」をしっかり確認し、その価値に納得できるかを判断基準にするとよいでしょう。


ここまで値上げの理由を解説してきましたが、そうはいっても納得できない人もいらっしゃるでしょう。
その理由について、まずは深ぼってみます。
納得できないと感じるときの理由4選
もし、たった一通のメールや書面で事前の相談もなく金額だけを知らされたら、多くの担当者は困惑しますよね。
日々の運用に大きく関わる費用だからこそ、調整や検討の時間が必要なのに、既に決定事項として一方的に通告されると「こちらの事情は無視なのか」と不信感が募るのもわかります。
信頼関係を築いてきたつもりなのに説明や配慮がない対応をされると、その信頼も揺らいでしまいますよね。
費用だけでなく、こうした“姿勢”の変化に敏感になってしまうのも当然だと思います。
値上げの説明を受けても「そもそも、保守で何をやってもらっているのかがよく分からない」という状態で保守サービスを受けているのではないでしょうか?
もし、月額で保守費用を支払っていても、報告がなかったり作業履歴が曖昧だったりすると「これまで通りで十分なのでは?」という気持ちになるのは当然だと思います。
システムが安定して動いているのはありがたいことですが、それが“何もしていない”ように見えてしまう状態なら、コストの正当性を感じにくいのも無理はありませんし、これをきっかけに開発会社からの報告の必要性も感じるところではありますよね。
正直なところ、値上げの話が出る前から対応に対して不満を感じていた場合、値上げの話は“追い打ち”に感じてしまいますよね。
問い合わせへの返答が遅かったり、ミスが繰り返されたり、お願いした修正に時間がかかったりなど、小さな不満が積もっていたのでは、値上げに不信感が募るのも無理はありません。
これまでの対応品質と照らし合わせたとき「この金額に見合うサービスを受けていたか?」という疑問が湧くのであれば、もしかすると保守サービスを受ける開発会社を変更することも視野に入れたほうがいいのかもしれません。
最近になって他社の保守サービスについて知る機会があった時、同じようなサービス内容で費用が他社よりも大きく上回っていた場合は、これまでの支出に対して「高すぎたのでは?」と疑念を抱くのも無理はありません。
もちろん、費用だけでサービスの良し悪しは測れませんが、相場を大きく上回る金額が提示されると「長年付き合ってきた会社なのに、足元を見られているのでは?」と不信感が生まれてしまうのも無理はありません。
もし「値上げ後の価格が値上げ前の30%以上」となる場合は特別な理由がない限りありえない金額だと思いますが、運用していて細かな仕様変更などがあった場合は、値上げも考えられる範囲かと思いますので、値上げの理由を明確にした上で検討されることが必要です。


では、値上げの理由別に対処法や交渉ポイントをお伝えしていきます。
【理由別】対処法・交渉のポイント
対処法:他社と比較し妥当性をチェックする
人件費や物価の高騰は社会全体の流れとして理解はできますが、「人件費や物価高騰がどこまで保守費用に影響しているのか?」は見えにくい部分ではないでしょうか。
相場感を確認したうえで金額が近ければ納得できるかもしれませんが、逆にあまりに差があるようなら理由の再確認や交渉余地を探る材料になります。
“人件費上昇”という漠然とした言葉に対し、具体的な数字で向き合うことが交渉のポイントです。
交渉のポイント:相場とあまりに価格が違う場合は、理由の再確認と追求を行う
対処法:実際の工数・作業範囲を確認する
機能の追加やシステムの拡張が進むと、保守の対象範囲も広がります。
ただ「規模の拡大=自動的に値上げ」とは限りません。
まずは「どの作業が増えたのか」や「工数としてどれくらい影響しているのか」を具体的に尋ねてみましょう。
作業項目や対象範囲の可視化を通じて、金額と内容が釣り合っているかを冷静に見極めることが大切です。
交渉のポイント:あまりに値上げ額が大きい場合は、工数の根拠までしっかり追求する
対処法:正式な書面での見積・説明を求める
契約更新時や初年度特別価格終了に伴う値上げは、当初の想定通りというケースが多いです。
ただし、それが事前に明示されていたか、説明が丁寧に行われたかがポイントになります。
更新後の正式な費用や対象範囲を、見積書や契約条件として明文化してもらいましょう。
まずは契約内容と費用の整合性を冷静に確認することで、建設的な対話ができるようになります。
交渉のポイント:もし事前に明記されていなかった場合は、改めて保守サービスの見直しを提案する
対処法:実際の工数・作業範囲を確認する
OSやクラウドの仕様変更などは、実際には保守負担が大きくなる場合があります。
しかし、その負担量は目に見えづらいものですので「どの部分に対応が必要で」、「それが保守にどの程度影響するのか」を明らかにしてもらうことが大切です。
“見えない作業”の内容を可視化することが、納得してサービスを受けたり交渉する際のカギとなります。
交渉のポイント:あまりに高額だと感じた場合、工数を確認したり保守サービスをより見える化してもらう
対処法:サービス内容の詳細を要求する
「サポート範囲を広げた」という報告だけでは、値上げの正当性を判断するのは難しいですよね。
この場合は、具体的に何のサポート内容が加わったのか、どう強化されたのかを明確にしてもらうことが必要です。
そして、プラスされたサービス内容に対して費用が妥当かを検討します。
サービスの質や量の“見える化”を求めることで、費用と価値のバランスが判断しやすくなります。
交渉のポイント:あまりに高額だと感じた場合、サービス内容を見直しするか、他社への乗り換えを検討する


保守会社の乗り換えを検討する主な理由は費用ですが、費用以外にも判断材料として確認した方が良いポイントがあります。
保守会社を乗り換えるべきか? 判断のポイント
大切なのは“高いか安いか”ではなく“その金額に納得できるか”です。
具体的な作業内容、対応範囲、体制などを知った上で「この金額なら妥当だ」と思えるかどうかが判断の軸になります。
内容が見えないまま値上げだけを通知されれば不信感が生まれると思いますが、透明性があり根拠も明確なら納得できるでしょう。
費用の数字そのものも大切ですが、開発会社の姿勢にも注目しましょう。
システム保守は、単なる契約ではなく“信頼関係の積み重ね”で成り立っています。
連絡したときの対応速度や言葉の丁寧さ、トラブル発生時の動き方などから、担当者への信頼感は少しずつ形成されていきますよね。
もし日頃の対応に不安を感じていたり、意思疎通が難しいと感じているなら、金額に関係なく今後の継続には慎重になったほうがいいでしょう。
「何かあったとき、この人たちなら任せられる」と思えるかどうかが、乗り換えを検討する際の大きな判断材料になるはずです。
別会社への乗り換えを検討する際、最初に確認すべきは“ソースコードや設計書などの資産が自社で保有できているかどうか”です。
もしドキュメントが未整備だったり、コードに独自ロジックが多くて引き継ぎが難しい状態であれば、乗り換えが難しい場合があります。
現状のドキュメントの整備状況を棚卸しし、技術的な独立性があるかどうかを確認することで、乗り換えするほうがコスト減になるかどうかを考えましょう。
他の会社でも保守が可能かどうかは、現実的な乗り換えができるかどうかに関わってきます。
「引継ぎ保守」を積極的に行っている開発会社もありますが、自社のシステムが対象かどうかは事前に調査しておく必要があります。
“引き継げる現実性があるか”を客観的にチェックすることで、乗り換えが選択肢として成立するかどうかを考えましょう。


突然の保守費用の値上げに、不安や不信感を抱くのはごく自然な反応です。
でも、大切なのは感情だけで判断せず、冷静に状況を整理することです。
値上げの背景には理由があるかもしれませんし、それが納得できないものであれば、改善や見直しを求める権利もあります。
まずは「なぜそうなったのか?」を見極め、自社にとって何が最善かを考えてみてください。
納得できる選択をするための第一歩は、“違和感をそのままにしないこと”です。
ここまで、よくある値上げの理由や、背景への向き合い方、「このまま続けるべきか・乗り換えるべきか」の判断軸をお伝えしていきました。
弊社も開発会社であるため、このように整理しておくことで”顧客との信頼関係の重要さ”を身にしみて感じたところであります。
弊社では開発も承っていますが、さまざまなシステム開発会社のご紹介事業も行っております。
複数見積もりも可能ですし、開発会社の紹介を受けるのに手数料などは一切かかりません。
もしよろしければ、ぜひご相談くださいね。



気になっているけど、まだ動けていない…
そんな方に向けて、全8回の無料メルマガを配信しています。
外注初心者でも安心して使える開発会社選びの考え方と
失敗しないためのチェックポイントをまとめました。
\ 名前とメールアドレスだけ!登録はこちら /