システム開発で使える補助金|申請方法や開発会社の選び方を解説

業務システムや基幹システム、Webシステムを新しく導入しようと検討している企業担当者は、できる限り導入コストを下げつつ自社に合ったシステムを導入したいとお考えかと思います。
そんな担当者に向けて「システム開発に使える補助金の申請方法」や「システム開発会社の選び方」を徹底解説していきます。
効率よく・無駄なく御社の業務改善を実現させるため、20年以上開発に携わる弊社目線でお伝えしていきます。
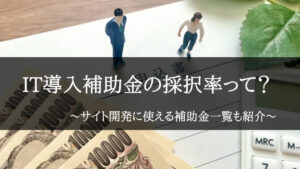
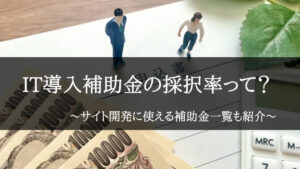
開発ジャンル別 利用可能な補助金


システム開発は企業の業務効率化や競争力強化に不可欠ですが、初期投資が大きな課題となることがあります。
そこで活用したいのが各種補助金制度です。
ここでは、システム開発の開発ジャンル別に、使える補助金の詳細と申請のポイントを解説します。
業務システム(基幹システムを含む)
業務システムとは、業務を効率化するためのシステムのことを言います。
- 会計管理
- 販売管理
- 生産管理
- 人事管理
- 勤怠管理
- 営業管理
- 顧客管理
業務システムの開発には、IT導入補助金が活用できます。
IT導入補助金は、業務効率化に資するソフトウェア導入に対して最大450万円の補助金の利用が可能で、「通常枠」と「インボイス枠」によって補助率や補助額の上限が変わります。
IT導入補助金「通常枠」
補助金テーマ:自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
補助上限額(補助率):5~450万円(費用の1/2以内)
IT導入補助金「インボイス枠」
補助金テーマ:インボイス制度に対応したシステム(会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、PC・ハードウェア等)を導入し労働生産性の向上をサポート
補助上限額(補助率):10~350万円(費用の1/2~4/5以内)
制御システムのセキュリティ対策(ネットワーク監視や端末監視)
産業用制御システムと呼ばれる、工場などでの監視・制御・生産・加工を担うシステムにおいて、近年はクラウド化が進んでいますが、クラウド化が進むにあたって不安なのは「セキュリティ面」ですよね。
そんな”制御システムのセキュリティ対策”にも補助金の利用が可能です。
利用できる補助金はIT導入補助金の「セキュリティ対策推進枠」。
補助率は費用の1/2以内で、補助額としては5万円〜100万円となっています。
IT導入補助金「セキュリティ対策推進枠」
補助金テーマ:サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
補助上限額(補助率):5~100万円(費用の1/2以内)
Webシステム(Webサイトなど)
Webシステムの開発には、さまざまな補助金が対象となります。
- ものづくり補助金(中小企業、小規模事業者向け)
- 新事業進出補助金(中小企業、小規模事業者向け)
- 小規模事業者持続化補助金(小規模事業者向け)
小規模事業者持続化補助金については、企業サイトなどのWebサイトにも利用が可能な補助金です。
また、ECサイトの構築やオンライン予約システムの導入など、販路開拓や新サービスの開発などの場合は、ものづくり補助金と新事業進出補助金が対象となります。
ものづくり補助金(中小企業、小規模事業者向け)
補助金テーマ:中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援
補助上限額(補助率):750~2,500万円(費用の1/2~2/3以内)
新事業進出補助金(中小企業、小規模事業者向け)
補助金テーマ:既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援
補助上限額(補助率):750~7,000万円(費用の1/2以内)
小規模事業者持続化補助金(小規模事業者向け)
補助金テーマ:小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援
補助上限額(補助率):50~200万円(費用の2/3~3/4以内)
補助金の申請方法
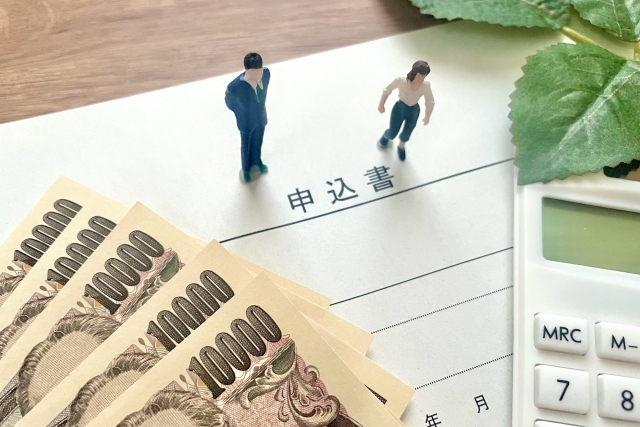
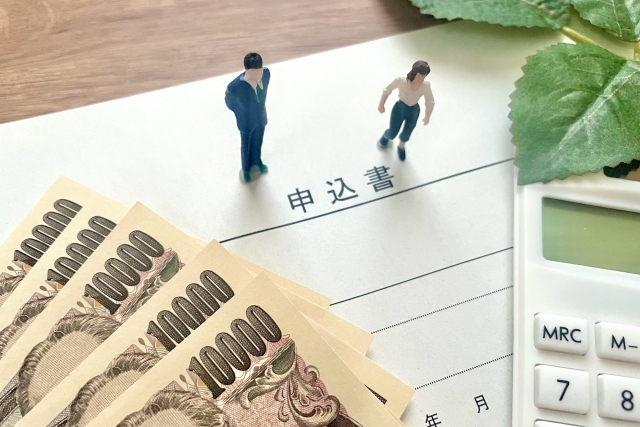
ここからは、補助金の申請方法について詳しく解説していきます。
自社で申請する
自社で申請を行う場合に必要なプロセスを解説します。補助金の申請プロセスは以下の通りです。
最近はオンラインで申請することが多いですね。
利用可能な制度を調査する
申請に必要な事業計画を作成する
必要書類を揃え、記入する
期限内に申請書類を提出する
書類審査や面接審査を受ける
審査通過後、交付が決定
計画に基づいて事業を実施する
事業終了後、成果報告を提出する
自治体の制度によって細かい部分が異なる場合があるので、詳しい内容は各補助金の制度内容をご確認ください。
専門家を活用する
補助金の制度は国が定めているため、個人や特定の知識を持たない人でも申請することは可能です。
しかし、国の補助金制度に関する申請は、複雑なものが多くて大変だという声をよく聞きます。
そういった場合、より効率的に申請を行い採択率を上げるために、専門家によるサポートを受けるという選択肢もあります。
- 中小企業診断士:経営戦略の観点から事業計画の策定をサポート
- 税理士・公認会計士:財務面での分析や投資効果の算出をサポート
- 地域の商工会議所や商工会:地域の特性を踏まえたアドバイスを提供
自社の状況や課題に応じて、適切な専門家を選択していきましょう。
しかし「専門家のサポートが受けられるんだ」と理解してもなお、



専門家を利用するって、本当に大丈夫?
と疑いたくなる方もいらっしゃるでしょう。
自分で申請することももちろんできますが、まずはメリットとデメリットを整理していきます。
まずは、多くの方が感じておられるであろうデメリットについて見ていきましょう。
- プロに依頼するため、費用がかかる
- 申請に関することすべてを丸投げにできるわけではない
これは、ある意味当然のことではあるのですが、申請に関わる費用は当然かかってきます。これが、自社で申請する時との決定的な違いです。
しかし、もし申請に落ちてしまえば、補助金を受け取れませんよね。
プロに頼んでも100%採択されるわけではないですが、補助金が下りれば費用を大幅に抑えられることはわかっていただけるかと思います。
また、専門家といえどクライアントについて全て知っているわけではありません。
必要な情報を伝えるためにはクライアント自身がある程度動かなければならないということも、頭に入れていただければと思います。
では、メリットはどのようなものがあるか見ていきましょう。
- 自社にとっての最適な補助金制度が何か分かる
- 申請書類の質が向上し、採択率が高まる
- 事業計画の策定や効果の数値化をサポートしてもらえる
- 申請プロセスの効率化が図れる
このように、まとめると「何もわからない状態でも、採択までの道のりを作ってくれる」のが一番のメリットではないかと思います。
補助金に詳しくない場合、申請書類の用意や、どの補助金が事業にとって最適かを理解するのにかなり時間を要してしまうでしょう。
安心できる専門家を探して、頼ってみるという選択肢もぜひ選んでみてほしいです。
セルバでも補助金の申請サポートを行っていますが、ITに強い専門家と提携しているため、高い採択率を実現できています。
システム開発を考えている企業担当者様は、ぜひご相談ください。
採択率を上げる方法
採択率を上げるためには、まず採択率に影響を与える要因を知っておく必要がありますよね。
一般的に言われている「採択率に影響を与える要因」は以下の通りです。
- 申請書類の完成度
- 事業計画の具体性と実現可能性
- システム導入による生産性向上や利益向上の見込み
- 予算枠と申請数のバランス
- 政策的優先度との整合性
これらの要因を十分に考慮し、質の高い申請を行うことが採択率を上げるカギとなります。
これらを踏まえたうえで、採択されやすい資料の作成ポイントを見ていきましょう。
採択されやすい事業計画のポイント
- 自社の経営課題とシステム導入によって解決したい具体的な問題点を挙げる
- 短期的・中長期的な目標を数値目標として設定する
- システム導入後の業務プロセスや予測利益の変化を具体的に描く
これらの要素を盛り込むことで、説得力のある事業計画を作成できます。一つひとつ見ていきましょう。
◆自社の経営課題とシステム導入によって解決したい具体的な問題点を挙げる
以下について、できる限り具体的に挙げていきましょう。
【具体的な問題点の考え方】
- 元々抱えている経営課題がどのようなものか
- その課題によってどんな損失が生まれているか
- システム導入でその課題がどのように解決すると考えられるか
これは基本なようで一番重要な点ですので、しっかりと考えて取り組まれることをおすすめします。
◆短期的・中長期的な目標を数値目標として設定する
システム導入によって得られる効果や、その上での経営目標を具体的に示すことで、より説得力のある事業計画となります。
以下のような例を参考に、自社での取り組みを考えてみてください。
【短期的・中長期的な目標の例】
- 労働生産性の向上(例:1人当たりの売上高が、導入後1年で20%増加)
- 業務効率化(例:受注処理時間が、導入後3ヵ月で50%短縮)
- コスト削減(例:在庫管理コストが、導入後翌月には30%削減)
- 顧客満足度の向上(例:顧客対応時間が、導入後半年で40%短縮)
- 新規顧客の獲得(例:新規顧客数が、導入後1年で年間15%増加)
◆システム導入後の業務プロセスや予測利益の変化を具体的に描く
システム導入後、どのように業務が変化していくのかを、具体的にわかりやすく記載することも必須です。
まずは申請者側がしっかりとイメージできること、そしてそのイメージをそのまま伝えられるようにすることが大切です。
以下の点をしっかりと押さえて、導入後をイメージしていきましょう。
【システム導入後をイメージするときに考えておきたいポイント】
- 導入するITツールの詳細(機能、価格など)
- 補助金で賄える部分と自己負担部分の明確化
- 導入後のランニングコストの見込み
- 投資回収の見込み期間
- 業務改善における見込み効果(期間、数値)
システム開発会社の選び方


開発会社目線で伝える、必ず見るべきポイント3選
- 開発実績
- サービスの柔軟性
- サービスのサポート体制
◆開発実績
これは言うまでもないですが、開発会社の開発実績を確認することは誰もが”重要だ”と感じるポイントですよね。
では、どのように実績を見ていけばよいのでしょうか?
開発実績は、企業によって公開内容がさまざまなのと、取引企業が公開NGとしている場合があるため、一概に全ての開発実績が大事とは言えませんが、実績数が多いから何でもいいというわけではありません。
開発実績を見るうえで重要視するポイントは以下の通りです。
【開発実績を見るうえで重要視するポイント】
- 開発実績件数
- 自社と同業の実績歴があるか
- 自社が求める開発に合った実績があるか
開発会社を選ぶ際に重要なのは「自社が求めるものを形にしてくれるかどうか」。
それを見極めるために、まずはどんなシステムを構築したいのか具体的にイメージし、求めるイメージと似たシステムの開発を実績として持っているかどうかが大きな判断基準になります。
”どこの”実績があるかではなく、”どんな”実績があるかを注視してみましょう。
◆サービスの柔軟性
これは見積もりを取ってみないとわからない場合もありますが、基本的に以下のような基準で開発サービスの柔軟性を見ていきます。
【開発サービスの柔軟性を見る基準】
- 社内でシステムを利用するときに専門知識がなくても利用可能かどうか
- 機能改修や追加などのカスタマイズが可能かどうか
- 開発後の保守対応が柔軟かどうか
これらは”ただ言われたままの内容で開発している会社”なのか、”幅広い提案をくれる会社”なのかを判断する基準にもなります。
自社でどれだけ具体的に「こんなシステムが欲しい」とイメージしていても、開発のプロほどの知識があるわけではありません。
近年のシステム傾向や流行などに詳しい開発会社であれば、提示してくれる内容が多岐にわたることもあります。
また提案力のある会社だと、希望する機能が予算内で実現不可能な場合、予算内で実現可能な別の機能を提案してくれることもあります。
まずは自社の要望と合致するかどうかをしっかりと見極めたうえで、さまざまな実装スキルがある会社に見積書を依頼すると、時間や費用に対するコスパも良くなります。
◆サービスのサポート体制
これは、見積もりを取って、実際にやり取りしてみないと分からない部分です。
判断基準は以下の通りです。
【開発サービスのサポート体制を見る基準】
- 営業担当者の提案内容が充実しているかどうか
- 実際進めていくとなるとどういうやり取りになっていくのかを明示してくれるか
- 担当者とのやりとりがスムーズかどうか
実際に見積もりを取った後に開発会社とやり取りをする際、しっかりと自社に寄り添ってくれる企業なのかを判断する基準となります。
やり取りが透明性高くできていると、開発会社も、開発を依頼する会社も、お互いが安心してやり取りすることができ、スムーズにシステム開発が進みます。
しかし、「窓口が営業担当で、細かい状況を共有しづらい」といった場合、開発進捗はもちろん、開発における意向を上手く汲み取ってくれるかどうかも怪しくなり、思っていたシステムに仕上がらないといったトラブルも起きてしまいます。
見積もりを取った際には「ディレクターと直接やり取りすることは可能ですか?」や「開発時はどういうやり取りになりますか?」などしっかりと疑問をぶつけてみるのがいいでしょう。
開発会社目線で伝える、依頼する前に注意すべきポイント3選
ここまで”開発会社を選ぶポイント”を解説してきましたが、やはり数多くある開発会社の中から自社にとっての最適を見つけるのは困難かと思います。
では、開発会社を選び、依頼をする際にどのようなことに気を付ければいいかを、開発会社目線で解説していきます。
- 担当者との相性がいいかは重要
- セキュリティ面は入念に確認
- 複数社から見積もりを取る
◆担当者との相性がいいかは重要
開発を進めていく際、一番重要と言っても過言ではないかもしれません。
もちろん、技術力の高さや開発価格の安さは魅力的に感じるでしょう。
しかし、実際に開発担当者との相性が合わなければ、些細な質問ができなかったり、うまくコミュニケーションを取れなかったりして、出来上がったシステムが使いにくいものになってしまったり、納期が遅れるなどの事態になってしまうことも考えられます。
また、営業担当とだけ相性が良くても、開発においてはあまり意味がありません。
それよりも実際の開発担当者との相性を確認できるように、事前に開発担当者を紹介してもらうようにしましょう。
◆セキュリティ面は入念に確認
最近は「ノーコード開発」というものが存在し、業務システムなどもその例外ではありません。
「ノーコード開発」というのは、前述したように、システム開発時に行う「プログラミング」に関する知識がなくても開発が行えるというもので、安価で早く完成できるので需要が高まっている開発サービスです。
しかし、懸念点は「セキュリティ面」。
全くセキュリティがないわけでもないですし、「ノーコード」でもセキュリティに強い会社は存在しますが、「プログラミング会社」よりは劣ってしまうことが多いのも事実です。
業務システムやWebシステムは、業種によりかなり多くの個人情報が集まる場所にもなり得ます。
そこはユーザーの信頼度を保つためにも、しっかりとしたセキュリティのある会社に任せたいですよね。
ぜひ見積もり時に、開発会社へセキュリティ面での対策などについて質問されることをおすすめします。
◆複数社から見積もりを取る
ここまでたくさんの注意ポイントをお伝えしてきましたが、やはり大切なのは”比較”することです。
特にシステム開発に関して知識が少ない場合、1社のみに絞って見積書を依頼すると、相場感や対応の差などを比較することなく開発まで進んでしまうことになるので、非常に危険です。
複数のシステム開発会社に見積書を依頼し、金額面だけでなく、対応や開発内容などを比較検討する材料にしましょう。そうすることで、より自社に合ったシステム開発を行うことが可能になるでしょう。
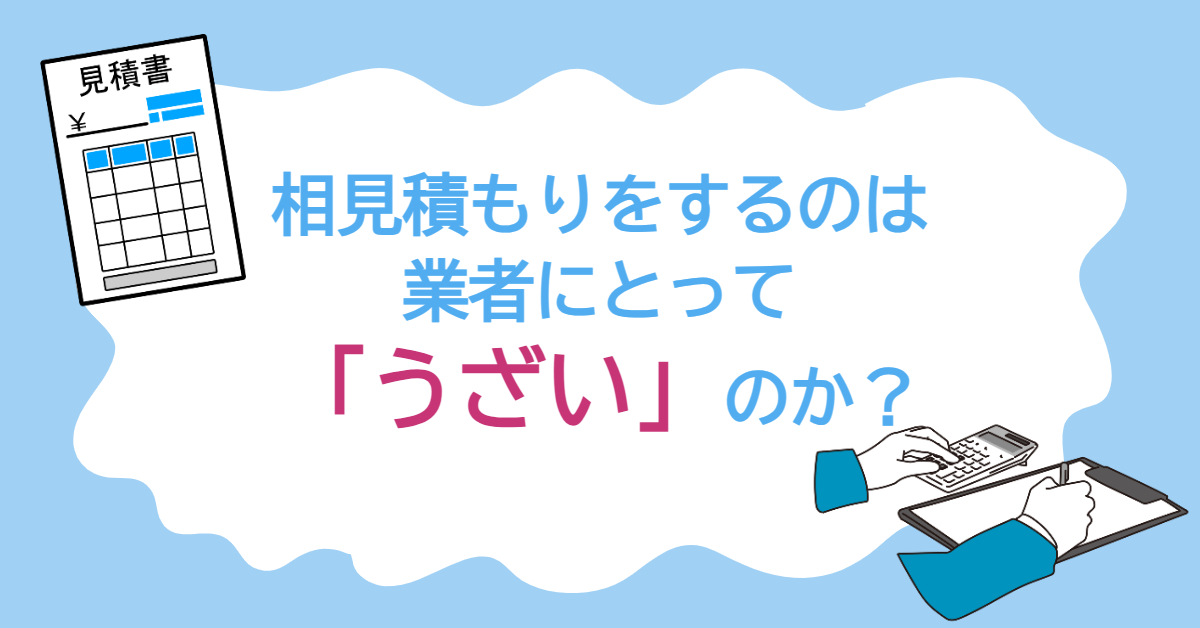
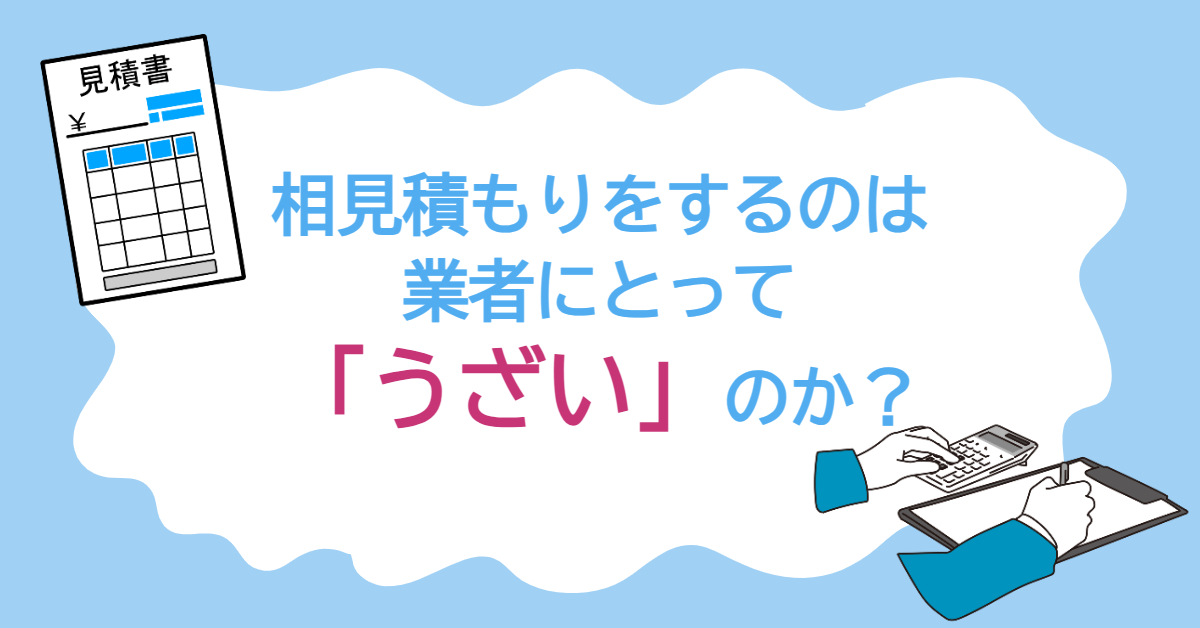
まとめ
業務システムや基幹システム、Webシステムを新しく導入しようと検討している企業担当者に向けて「システム開発に使える補助金の申請方法」や「システム開発会社の選び方」を解説していきました。
せっかくシステムを導入するなら、できる限り低コストかつ自社に合ったシステム開発を確実に行っていきたいですよね。
しかし「補助金」というものは、申請すれば必ず採択されるとは限らず、手間もかなりかかってしまうため、近年では専門家に依頼しているケースが急増しているようです。
弊社も例に漏れず、補助金申請の支援を行うことのできるシステム開発会社です。
補助金申請支援サービスのみのご利用も可能ですし、システム開発会社選びのお手伝いもできますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
補助金取りこぼしを無料で診断『セルサポ』▼(画像をクリック)



