エージェント経由で転職してきた人がすぐ退職するトラブルを防ぐ方法

近年の転職方法としてよく利用される”転職エージェント”。
いわゆる人材紹介サービスで、転職エージェントによって採用活動を進めている企業は多いかと思いますが、ようやく採用に至ったのにすぐに辞めてしまったということはないでしょうか?
企業としては、せっかく採用したのだから、すぐに辞めてほしくはないはず。
辞めてしまう人の心理を分析して、入社後すぐの退職を防ぐためにできる企業側の対策法について考えていきます。
また、人材事業を行う企業として、人材紹介会社ができる対策についても解説します。
エージェントを利用した採用活動とは?


では、まず「転職エージェント」について理解を深めていきましょう。
転職エージェントについて記載したものは以下の通りです。
転職エージェント(人材紹介会社)は、転職を希望するあなたのアドバイザーであり、最適な求人を紹介します。登録をすると一人ひとりに担当が付き、さまざまな相談に乗ってくれるのが特徴です。
一方で、企業から求人を預かるのも転職エージェントの役割のひとつです。つまり、転職を希望するあなたと企業側をつなぐ架け橋として、双方の利益のために存在するのが転職エージェントなのです。
引用元:エンエージェント
このように、「早く新しい就職先を決めたい」と考えている求職者や「早く採用を決めたい」と思っている企業側の架け橋となるように、さまざまなサポートをしてくれる存在です。
この採用活動手法を、「企業側」と「求職者側」に分解して考えてみましょう。
企業側が人材紹介を利用する理由
では、転職エージェント、いわゆる人材紹介会社を利用している企業について考えてみます。
まず、企業が人材紹介会社のサービスを利用する理由は何でしょうか?
- 優秀な人材を採用したいから
- 採用に対する工数を削減したいから
- 長期にわたって求人情報の掲載を行うよりもコスパがいいから
体感としても、だいたいこのあたりの理由が多くなってきます。
企業にとって、採用活動はとても重要な役割だと言えますが、近年では特に、苦戦してしまうことが往々にしてあります。
その状況で採用活動を行っていくとなると、「いかにマッチした人材を受け取れるか」が大切になってきます。
求職者が転職エージェントを利用する理由
では、求職者がエージェントを利用する理由は何でしょうか?
- 非公開求人を見たい
- 転職活動をトータルでサポートしてほしい
- 自分に合った転職先を効率よく探したい
このように、自分1人だけで求職活動を行うよりも、より効率的に且つ確実に就職先を探したいという場合に利用する手段になっていることが多いです。
転職活動時に求職者は、企業の紹介を受けるだけでなく、履歴書やエントリーシートの添削、面接対策、面接日程の調整、入社条件の交渉の代行など多岐にわたって無料でサポートを受けられます。
すぐ辞めてしまう人はなぜいるのか?
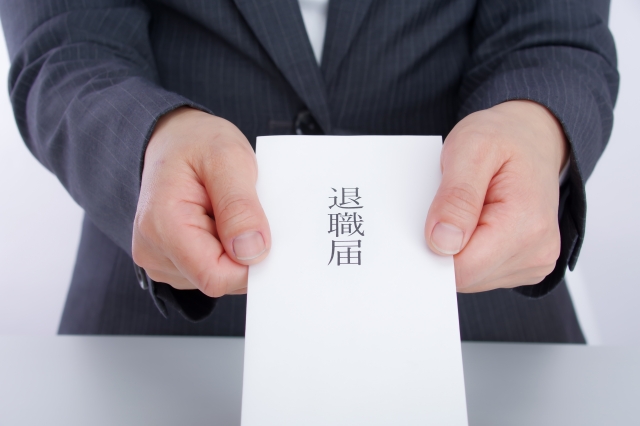
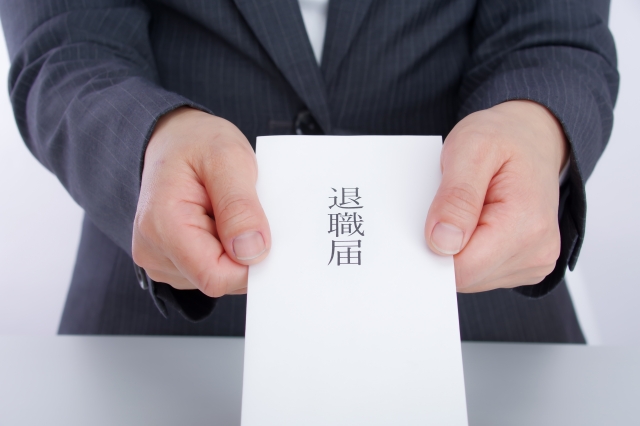
では、そんな手厚いサポートを受けながらも、就職先を辞めてしまう人はなぜ発生するのでしょうか?
辞めてしまう人の心理を読みながら、その対策について考えてみましょう。
すぐ辞めてしまう人の心理
まずは、辞めてしまう人について書かれたXのポストを覗いてみましょう。
これらを見ていると、「やる気があるように見える人」でもすぐ辞めてしまう人もいるし、就職先と自分の価値観にミスマッチがあると感じると、自身のキャリアを考えたときに落ち込む人もいるようです。
現在、転職市場は求職者の数よりも募集企業の方が多く存在しており、短期離職をしていても転職できるケースが多いです。
だからといって短期転職を肯定する気はありませんが、リスクを冒してまでも短期転職を促してしまう「企業と個人のミスマッチ」とはどういうものでしょうか?
短期離職をしてしまう人が感じる”ミスマッチ”
短期離職をしてしまう人が感じる”ミスマッチ”は以下のようなものがあると考えられます。
- 仕事内容が面接で聞いていた話や想像していたものと異なる
- 職場の雰囲気や文化が自分に合わない
- 責任の重さや業務量が予想以上である
このようなミスマッチは、確かに誰でも、どこの企業でも起こりうることです。
しかし、そのミスマッチを限りなくなくすために「転職エージェント」や「人材紹介」を利用しているはずなので、できる限りミスマッチを防げる採用活動を行いたいですよね。
そうなると、ミスマッチを防ぐために必要なのは「どこまでも求職者目線で仕事を紹介してくれるエージェント」ではないかと私は思いました。
確かに、人材紹介会社に報酬を渡すのは、サービスを利用している企業になるわけですが、企業側が求めているのは「ミスマッチのない人材の獲得」。
そのために求職者が応募企業に対してどんなイメージを持っているのかや、情報の伝え漏れ・誤りはないかどうかを確認することが非常に重要となります。
もちろん、求職者自身もエージェントに丸投げしたり何でもエージェントのせいにせず「ちゃんと自分に寄り添ってくれるエージェントなのか」を見極めて信頼し、就職先の決定まで並走してもらうようにすることが大切です。
そのために、求職者自身が自分の価値観をしっかりとエージェントに伝えられる環境であるかどうかが、エージェント会社に求められることではないかと思います。
企業側にも原因があるのか?
では、ミスマッチが起こることは、企業側にも原因があるのかについて解説していきます。
気になるXのポストを発見しました。
ここで言われている通り、「人材紹介を使ったから」というだけではいい人材を採用することはできず、エージェントに対して「どこまで企業側が能動的に動けるか」がいい採用活動を行うためのカギになります。
人材紹介を介した採用活動では、基本的に企業が直接求職者とやり取りをすることは禁じられています。
それを上手く活用して、面接が進んでいる採用予定者について、エージェントから見た意見を聞いてみたり、ミスマッチが起こらないように情報の擦り合わせを丁寧に行ったりして、企業側が積極的に人材紹介会社と関わっていくことが、人材紹介会社を利用する企業に求められることではないかと思います。
人が辞めないための対策とは?


では、せっかく人材紹介を利用するのですから、ミスマッチが起こらないようにするにはどんな工夫ができるのかについて考えてみましょう。
企業の採用担当者ができること
企業の採用担当者が、どんなことに気を付けて人材紹介会社を利用するのがいいかについて触れていきます。
- 自社の魅力を分かりやすく伝える
- 選考状況を細かく共有する
- 選考で不採用にした理由をしっかりと伝える
自社の魅力を分かりやすく伝える
人材紹介会社は、多くの求人情報を保有しています。そんな中、人材紹介会社が求職者に情報提供する際は、魅力がわかりやすい求人情報を優先的に紹介することになります。
そのため、ただ会社概要と求人情報を人材紹介会社に伝えるだけでは、何の魅力も伝わらないので、「自社で働くメリット」をわかりやすくまとめて人材紹介会社に伝えるなどの努力をすることで、いい人材を紹介してくれる可能性が高まることが期待できます。
また、自社で働く魅力は、決して条件面だけではありません。
社内でアンケートを取ってみたり、実際に働いている社員にヒアリングするなどして、「なぜ自社で働き続けたいと思うのか」を言語化することで、生の声を伝えることができ、求職者とのミスマッチを防ぐことにもつながります。
選考状況を細かく共有する
選考を進めていく中で、どのような進捗状況かを人材紹介会社が知ることができなければ、採用活動の手助けを行うことが難しくなってしまうでしょう。
そのため、仮に検討中だったとしても、どのような内容を検討しているのか、合否のどちらに近いのかなど、細かく情報共有を行うことで、お互いのミスマッチを防ぐようにしましょう。
選考で不採用にした理由をしっかりと伝える
選考で不採用になった場合、必ず理由があるかと思います。
しかしその理由が上手く言語化できておらず「なんとなく違和感があった」「雰囲気的に自社と合わないと思った」などの曖昧な表現になると、人材紹介会社からすると「どのような人材が受け入れてもらいやすいのか」が把握できなくなってしまいます。
そのため、不採用になった時ほど「求職者のこの発言が、自社の雰囲気に合わないと感じた」や「求職者のこのような雰囲気に違和感を覚えた」など、具体的に情報提供するようにしましょう。
人材紹介会社ができること
では、逆に人材紹介会社が気を付けるべきポイントについても触れていきましょう。
- 求職者が気持ちを打ち明けやすい環境を整える
- 企業側の要望を深掘りして理解を深める
求職者が気持ちを打ち明けやすい環境を整える
まず、人材紹介会社は「求職者ファースト」であってほしいと私は考えます。
なぜなら、マネタイズの対象は採用活動を行う企業ではありますが、「企業ファースト」で紹介事業を行ってしまった場合、求職者が納得した転職活動を行えず、なんとなくで入社してしまい、すぐ辞職し、収益が発生しないというリスクが大きくなるからです。
人材紹介会社は、求職者にとって「身代わり」のようなものです。
その会社に対して、求職者が本当に思っていることを打ち明けることができなければ、求職者自身が納得できる就職活動を行えなくなります。
転職先に求める条件だけでなく、なぜ辞職に至ったのか、今後やってみたいことはあるのかなど、しっかりとヒアリングできるように環境を整えましょう。
そして、噓偽りなく求職者が話してくれるようになれば、よりよい転職活動のサポートを行うことができます。
企業側の要望を深掘りして理解を深める
先ほど「求職者ファースト」と述べましたが、それは求職者のことを知ることだけではありません。
企業の情報をどれほど知っているかで、求職者にとって必要な情報をより多く届けられるかが決まります。
人材紹介会社が企業の情報収集を積極的に行えば、求職者と企業のミスマッチを防ぐことができます。
まとめ
転職エージェント、いわゆる人材紹介を利用する上で気を付けるべきことや、その企業側と人材紹介会社側の対策法について解説しました。
人材紹介は、求人広告などと比べてミスマッチを防ぎやすい採用活動手法として知られています。
その理由は、人が人に紹介をするからです。
その本質を理解して、企業側・紹介会社側がどのように向き合うかで、結果は必ず変わってくるのではないでしょうか。
この気付きが、よりよい採用活動の一助となれば幸いです。
弊社では求人サイトの開発・運営のほか、人材紹介会社・人材派遣会社への集客支援も行っております。
集客や求人サイトの制作・運用など、人材事業についてお困りの場合はぜひご相談ください。


